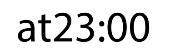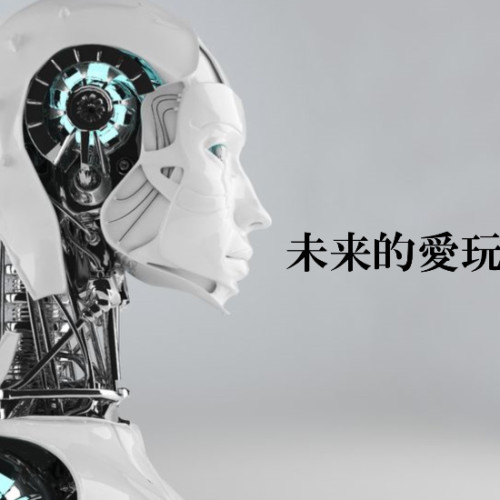Put back over spilt milk

男とケンカをした女は、その親友の男をBARに呼び寄せる。男と女は It’s no use crying over spilt milk.(覆水盆に返らず)こぼれたミルクをは元に戻せるのでしょうか・・・
※このドラマは音声で聞くことが出来ます。
荻野奈緒
荻野奈緒がその店の木造りのドアを開けたのは、まだ開店して間もない時間だった。馴染みのバーテンが奈緒を見て、少し驚いた顔をした。
「もう、いいかしら」
奈緒は親しげな顔でバーテンにそう聞きながらも、すでにストゥールを引いて愛用のブルガリのバッグを椅子に置いた。
「今日はやけに早いですね」
若いバーテンが、洗い物のグラスを磨きながら奈緒に言った。
「ええ、仕事終わりが今日は神戸だったから。ビールを頂戴」
カウンターの上に積み上げている陶器の灰皿を奈緒は勝手知ったようにひとつ取り、メンソール煙草に火をつけている。
派遣社員の奈緒は定期的に販売場所が変わる。京都、大阪、神戸の決められた販売所が彼女の職場だった。職業柄彼女の服装はいつも垢抜けている。
身につけている小物は、27才なのでそう高価なものはいつもつけられないだろうが、彼女が付けるとどれも高価に見えるのは彼女が持つ華のある雰囲気からきているのだろう。
「おつかれさまです」
若いバーテンは、奈緒の前に模範的な泡の配分のビールを置いた。
「ありがと」
奈緒は、ビールを三分の一ほどぐいと飲み、その綺麗に揃った両の眉を少し上げて、バーテンに「美味しい」という表情を作ってみせた。バーテンもその奈緒の表情に笑顔で答えた。
「青山さんは後でお見えになるんですか?」
若いバーテンは、再びグラスを磨きながら奈緒に尋ねた。
「知らない」
「そうですか」
バーテンはそれ以上のことを奈緒に聞かなかった。明らかに奈緒の表情からは不機嫌な雰囲気が漂っていたからだ。若いながらもそのバーテンは心得ている。
「でも誰かと飲みたいわ」
奈緒は、誰に言うでもなくそう言った。ある程度経験があるマスターなら気の利いたセリフのひとつでも彼女に言ったであろうが、その若いバーテンにはまだそれほどの経験はなかった。なんとか仕事をするフリをして奈緒のいる場所から少し離れるのが精一杯の気の使いようだった。
奈緒は、左手に持つ二つ折りの携帯電話を開けてみた。ジョグダイヤルをかなり手馴れた指の動きで動かしていく。見慣れない者では、その表示が読み取れないのではなかろうかという速さで表示文字が過ぎていく。送りながら時折指の動きを止め、再び表示画面を替えていく。そしてある名前のところで、奈緒は小首をかしげた。
表示画面を眺めながら、奈緒はビールを一口飲んだ。そして綺麗にマニュキアの塗られた指で、これまた器用にボタンをプッシュしていった。文字は『飲みたい。グランブルー』とだけあった。最後のプッシュと共に画面はアニメな動きになってメールが送信された。
グランブルーというのは、今奈緒がいるBARの名前だった。名前の通り店内は深いブルー調で彩られており、まるで深海に居るような錯覚になる造りの店内だ。
青木が気に入ってる店で、半年ほど前に連れて来られて奈緒も気に入った。同僚の女友達も数人連れてきたが、みんな雰囲気がいいと気に入ってくれた。青山と奈緒はすでに8ヶ月前からスティディの関係となっている。
見慣れた店内を見るともなく、奈緒は半年前に来た頃を思い出して眺めた。手元のグラスにはビールがすでに残り少なくなっている。その最後の一口を飲み終えた時に、奈緒の携帯の着信メロディーがまだ客のいない店内に響いた。
奈緒は左手だけで二つ折りの携帯を開いて、画面をみた。
『後20分』
とだけ、表示画面にはあった。それを見た奈緒は椅子に座りなおして、ひとつ溜息をついた。そしてバーテンにビールのお代わりを告げた。
神田三郎
神田三郎が店に現れたのは、奈緒が先ほど携帯を見てから丁度20分ほど経ってのことだった。奈緒は、飲み物をジンに替えていた。
「いらっしゃいませ」
バーテンの声に、笑顔だけで神田は答えた。長身の神田は黒のロングコートが似合っていた。ストゥールを引いて、神田は奈緒の横に無造作に座った。
「バーボンロック」
神田はバーテンにすぐに言った。
「飲んでたの?」
「うん」
神田は奈緒を見てそういった。
「近くで?」
「運良く」
「お邪魔した?」
「いいや、もう別れたい客だったんだ。奈緒ちゃんの着信で会社から帰れと言われたと別れる理由が出来た。グッドタイミングだった。サンキュー」
バーテンが、神田の前にコースターとロックグラスを置いた。神田はグラスを目の位置に少しあげ、奈緒に乾杯の仕草をしてから一口酒を飲んだ。横からだと前髪が目にかかり、その目の表情は見えないが鼻筋と口元だけで神田の端正な顔立ちは分かる。
青山も神田と同じくらいの背丈がある。二人は高校時代からの親友だった。そして青山の紹介で、奈緒は神田と会った。何度も三人で飲むうちに親しくなった間柄というわけだ。
青山と神田は高校時代サッカー部で一緒だったという。二人とも細身の長身で当時からさぞ女子生徒からはモテたであろうというのは安易に想像出来る。
社会人になってからも神田と青山は一番仲がよさそうだ。
「青山は来るのか?」
神田はセブンスターに火をつけながら、奈緒に聞いた。
「来ないわ。約束してないもん」
奈緒は、ちょっとスネるような口調で言った。「おや」というように、神田は奈緒を見た。
「そうか」
それだけ言うと、神田には合点がいった。
「飲みたいから付き合って」
「いいよ。どうせここで飲まなくても、どこかで飲む運命だったんだから」
奈緒は、自分のグラスを神田の置いてあるグラスに芝居かかった調子でガツンと当てた。そして少しおどけた表情で、神田の顔をみた。
酔っ払い女
10時を過ぎた店内は、常連の客で半ば埋まっていた。
奈緒はテキーラを飲んでいた。開店間もない時間から飲み続けていたので酔いも結構回っていた。神田は好みのスモークサーモンをつまんでいる。グラリと奈緒の身体が神田に寄りかかった。
「そろそろ撤退するか」
神田は自分の左肩にある奈緒の頭に向かって言った。
「いや、まだ飲むの」
「やめとけ、そんな飲み方は身体に悪い」
「尚之と同じ口調でそういうのはやめて」
尚之というのは青山の名だった。
「あいつと口調が似ているか?」
「そっくりだわ。あんた達ホモじゃないの」
「とにかく出るぞ」
神田はフラつく奈緒を立たせて、コートを着せた。レジまで奈緒の左腕をしっかり掴んで歩かせチェックを素早く済ませた。店は地下にあったので、二人は階段を歩いて地上まで出た。奈緒は一人では歩けないほど酔っていた。
「タクシーに乗せるぞ」
「いや、もう一軒行くの」
「嫌な客の方がよかった」
神田は冗談のつもりで独り言のように言った。
「なにぃ、嫌な客以下で悪かったわねぇ!」
嘘のキス
奈緒が神田にからんできた。神田は奈緒を抱くようにして、北野の街を駅方向へとりあえず歩き出した。
レンガ造りの風見鶏の館が闇の中では、その姿が日中よりも巨大に見える。その南側には神戸の夜景がある。しかし深夜ともなってライトの数は若干少なくなっているのかもしれない。
ここは北野坂の最北にある小さな公園だ。神田と奈緒は一旦駅の方向に向かったが、奈緒が突然夜景が見たいと言い出してここまで上がってきたのだ。
奈緒は頭一つ高い神田の腕に抱きつくようにして立っている。
二人はこうしていると、人目からは何不自然のない恋人にきっと見えることだろう。
「キスして」
奈緒が俯いたまま、神田に言った。神田は奈緒の言葉が聞こえたのか聞こえなかったのか分からないが奈緒を見た。
「キスしてよ」
奈緒は今度は顔を上げて、神田に言った。二人は暫く見詰め合った。そして奈緒が眼を閉じた。神田はゆっくりと奈緒の唇に自分の唇を重ね合わせた。時間にしておよそ10秒のキスだった。
しばらく二人は無言だった。風が一陣舞った。その風を待ってたように奈緒が神田に「行こうよ」と言った。
神田は、無言で奈緒を見詰めていた。無言の二人の尺を埋めるように、奈緒が神田の腕をひっぱった。
神田はゆっくりと首を横に振った。
奈緒は一瞬キョトンとした表情を見せたが、今度は探るように神田の顔を下から眺めた。
神田は再びゆっくりと首を横に振った。
奈緒はその神田の顔を仰ぎ見るようにしばらく見詰めていた。そしてスローモーションのように奈緒の表情が崩れて泣き顔になった。目元からは涙が溢れてきた。
奈緒は両手で顔を覆い、声を上げて泣いた。神田は泣いている奈緒をただじっと見詰めていた。奈緒が自分の頭を神田の胸に押し当てた時、はじめて神田は奈緒を抱きしめてやった。
奈緒は時間をかけて泣き続けた。時間とともに奈緒の嗚咽は小さくなった。神田はただじっとその間も奈緒を抱きしめていた。
泣き止んだ奈緒は、ゆっくりと神田を見上げた。少し微笑んで神田は奈緒を見た。そしてひとつ頷いただけで、奈緒を抱き締めたまま歩き出した。
北野の坂を神田と奈緒は、ゆっくりと降りてきた。
奈緒は軽く神田の腕に手をかけているだけだった。
「ごめんなさい」
奈緒は、小さく神田に言った。
「いいよ」
「ほんと?」
「どうせ、誰かに絡まれる夜だったんだ」
神田はニヤリと笑って奈緒に言った。その言葉が冗談だとわかった奈緒は、キツく神田の腕を自分に引き寄せた。
「青山と話し合え」
「そうする」
奈緒は素直に言った。その言葉の中に、自分がとった行動の反省が十分に含まれていた。
「罪悪感・・・」
と奈緒が独り言のように言った。
「なぜ?」
神田が奈緒に聞いた。
「だって、彼を裏切ったわ私」
「別に裏切ってないさ」
「さっき、あなたとキスしたわ」
神田が立ち止まった。奈緒もつられて立ち止まった。二人は道の途中で差し向かえになった。
「あれは嘘のキスだ」
「嘘のキス?」
「そうだ」
「なによ、嘘のキスって?」
「気持ちが全然入ってないから」
奈緒は再びキョトンとして長身の神田を見上げた。
「そんなのあるの。嘘のキスって」
「あるさ」
奈緒は、思案する顔でしばらく考えていた。
「昔、高校ぐらいの英語で習ったわ」
「なんて?」
「なんとかなんとかミルクって」
「なんだそれ?」
「ほら、こぼれたミルクはもう元に戻らないって」
「It’s no use crying over spilt milk. か」
「そうそう。だからもうダメよ」
「大丈夫さ」
神田は事も無げにそう言った。
「来いよ」
ミルクで乾杯
神田はいきなり歩き始めた。奈緒は神田の後を追うように歩き続けた。
BARグランブルーの店内は、すでに終電で帰る一時の客を越えて落ち着いていた。
カウンターには若いバーテンと入れ替わりに、年配のマスターがいた。神田と奈緒は先ほどいた同じ場所のカウンターに着いた。
奈緒は訳が分からないという風に神田を見た。神田は少しおもしろがるようにして奈緒にウィンクをした。
年配のマスターが二人の前にコースターを置いて、目だけでオーダーを聞いてきた。神田はマスターを見ずに奈緒を見ながら、
「ミルクをロックでふたつ」
と言った。マスターは聞き間違えたのかという顔をしていたが、神田の表情を見て頷いてからドリンクを作りはじめた。奈緒はちょっと驚きながら、神田の顔を不思議そうな表情で見た。
しばらくして二人の前に、オールドファッショングラスに丁度ダブルの量に入れられた白色の液体が出てきた。マスターはこれでいいかという風に神田を見た。マスターの眼はあきらかに笑っていた。それに答えて神田も笑顔で返した。
神田はそのグラスを手にして、奈緒を見た。
「ミルクが戻ったところで、さっきまでつかまっていた嫌な客のグチを聞いてくれるか?」
と神田は奈緒に言った。奈緒は再び泣きそうな表情になりながら、笑って大きく頷いた。そして、
「ありがとう」
と神田に言った。
おわり
「Put back over spilt milk」
Story by ushi