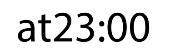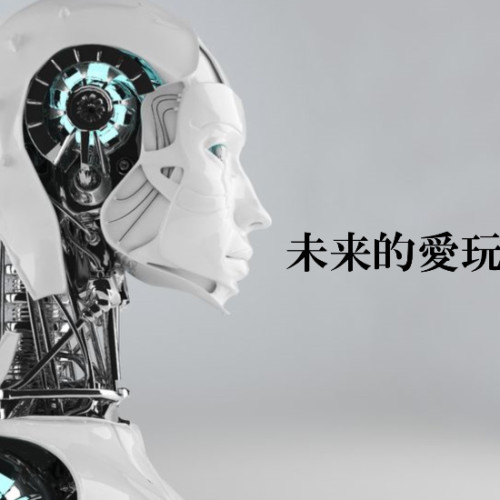あの日、桜の下で

心地よいジャズのスタンダードナンバーが鳴り響く。
全体に木目調を生かしたウッディ造りの店内は、長く居ても落ち着く雰囲気を醸し出している。
ダウンライトの灯りが等間隔に落ちているカウンターに今僕はいる。
サクラというリキュールを大き目の砕氷にロックグラスで飲んでいる。
グラスの中には桜の花びらがひとひら浮かんでいる。
毎年この季節になると僕はこれを飲む。
もう一人でこんなBARに来て飲む年齢になったのだとしみじみ思ったりもする。
チェイサーの代わりに今晩は10オンスタンブラーに桜の小枝を一輪刺している。
桜の花びらをつけたその小枝からは、僕にとっては懐かし匂いがする。
遠い幼い頃の甘い、そして優しい香りなのだ。
そしてその先の記憶には、あの優しい人の面影が浮かぶ・・・
僕が小学3年生の頃、近所にとても仲の良い吉川くんという子がいた。
古い日本建築で庭のある家だった。
マンション暮らしの僕は、庭がある吉川くんの家が羨ましかった。
吉川くんは学校が終わった夕方に、僕をよく家に招いてくれた。
子供の頃にする遊びを彼の家の庭でもよくして遊んだものだ。
庭は広くいろんな木々があった。
木の名前なんてほとんど知らなかったが、桜の木だけは春にはいっぱいピンクの花びらをつけるので子供の僕も唯一それだけは分かった。
遊んでいると吉川くんのお母さんは、僕達におやつをくれた。
それも吉川くんの家に遊びに行くひとつの楽しみだったのだ。
そして子供心にもうひとつの楽しみがあった。
吉川くんには5つ年上のお姉さんがおり、お母さんが留守の時はそのお姉さんがおやつを出してくれる。
子供の頃の5才違いというものは、それはとてつもなく年上の人であった。
小学生からみれば、もう立派な大人のようである。
お姉さんの名前は玲子さんと言った。
吉川くんの家で見かけるお姉さんは、制服のセーラー服の時もあり、すでに着替えて私服の時もあった。
いずれにしても小学生の同級の女の子にはない、なにか甘酸っぱい匂いがしていたのを覚えている。
吉川くんの家に遊びに行って、まだ吉川くんが帰っておらず居間で待たせてもらったことがある。
偶然早くに帰宅していたお姉さんが、気をきかしてくれたのであろう色々と喋りかけてくれた。
なぜか僕はその時、顔が熱くなり言葉が思うように出なくなった。
そんな体験ははじめてのことだった。
その時はなんで自分の心臓がこんなにドキドキしているのか分からなかった。
その理由がわかったのは、僕が中学生になってからのことだった。
あの日もいつものように学校で、帰ってから吉川くんの家で遊ぶ約束をした。
カバンだけを自宅に投げ入れて、自転車で10分くらいの吉川くんの家に行った。
すでに勝手知った友達の家だ。
門扉も自分の家のように何気に開けて、自転車を石畳を押して入る。
玄関横に邪魔にならないように自転車のスタンドを立てて、僕は振り向きざまに庭先をみた。
ひときわ大きな桜の木陰に何か蹲る物を感じた。
よくよく見ると、それは吉川くんのお姉さんだった。
不思議に思い、僕はお姉さんの元へゆっくりと近づいて行った。
かなりそばまで来たときに、お姉さんの肩が震えていることに気がついた。
僕が驚いて立ち止まった足元の気配で、お姉さんはしゃがんだまま振り返った。
僕は「あッ」と驚いた。
笑顔の時だけしか知らないお姉さんが、睫を濡らして泣いている。
僕は驚きのあまり動けなくなってしまった。
お姉さんは立ち上がり、僕を見た。
そして無理に笑顔を作ろうとしても、うまく出来ないような複雑な表情になった。
とても悲しいのだろうということだけは、子供心にも嫌というほど感じ取った。
誰かに叱られたのだろうか、いやお姉さんが誰かに叱られるなんてことはない。
苛められたのだと、咄嗟に僕は悟った。
「誰がお姉ちゃんを苛めたの!」
自分でも驚くほど大きな声を出したのを覚えている。
実際なんとも言い知れぬ怒りがそのときは込み上げてきた。
大切なものを、無造作に誰かに壊されたような怒りだった。
「苛められたのなら、僕が仕返ししてきてあげる」
とも言った。
しばらく僕の顔を見ていたお姉さんは、次第にいつもの優しい表情に戻っていった。
じっと佇む僕のところまで歩み寄って、
「誰にも苛められてないよ」
と言った。
でも僕はまだ信じられなかった。
「ちょっと悲しいことがあっただけなの、でももう大丈夫だから」
とお姉さんは、僕に笑顔で言った。
僕はそれ以上のことは聞けなかった。
なんだか聞いてはいけないことだと思ったからだ。
でもどこかに腑に落ちない思いは消えなかった。
「お姉ちゃんのことは、僕が守ってあげるよ」
行き場のない思いがそんな言葉になって出たのだろう。
お姉さんは、しばらく僕を見つめてそれから突然僕の顔に自分の顔を近づけた。
何が起こったのか僕はわからなかった。
以前感じた時よりも顔が熱くなり、その後何を話したのかまったく覚えていないのだ。
お姉さんはただ僕に
「ありがとう」
と言ってくれたのだけは、微かに覚えている。
数年後にそれが僕のファーストキスだったということと、お姉さんはあの時、誰か好きな人に振られたのではと思うようになった。
だから人知れず桜の木陰で涙してたのだ。
そう考えればあの時の状況が理解出来る。
でも今となればその事実を知る由はない。
それ以来もういくつもの桜の頃が過ぎ去った。
春の匂いが沸き立つこの季節になると、僕はあの人を思い出す。
春の、それも桜の香りは遠い幼い頃に僕が憧れの人だった思い出の香り。
いつかまた、あの桜がある家を訪ねてみようと思う。
いつになるかはわらかないけれど、僕の思い出があるあの桜を訪ねて・・・
おわり
「あの日、桜の下で」
Story by ushi